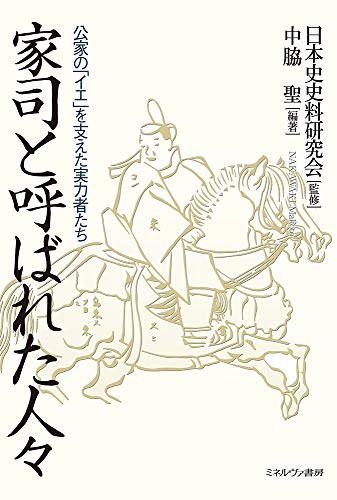近年歴史関係の本は充実していっている。背景として研究の深化があることは間違いないが、一昔前だとなかなか出ないようなテーマでの一般書が出版されている。出版不況が叫ばれて久しい中、マイナー気味なテーマでの出版が可能であることは、それだけでありがたいが、同時に需要自体が広がっているからこそでもあるのだろう。こうしたWIN-WIN関係が拡大しつつ継続していってほしいものである。
というところで近日発売されたのが『家司と呼ばれた人々』である。『伝奏と呼ばれた人々』の続編(?)的著作である。いやあスゴイ。一般人対象にアンケートとっても「伝奏」も「家司」も何なのかわからない人が多いのではなかろうか。それでも伝奏は「武家伝奏」という単語が朝幕関係では出来するのでまだ知っている人もいるかもしれない。これが家司となると完全に公家社会の中で完結してしまう存在(に見える)なので、公家社会にわざわざ突っ込んでいかないとわからない。そもそも鎌倉時代以降の公家社会というのは教科書でも触れられないし、それもあって一般的に影が薄い。私自身、家司って何?と問われても「公家に仕える公家」程度の合ってるかどうかの確信がない答えしか示せない。ましてや、具体的に活躍した家司など1人も名前を挙げて説明できない。私の不勉強さゆえだが、歴史ファンでもこういう人は多いのではなかろうか。
そんな中彗星の如く、家司とは何ぞや?を提示する一般書が出るのだから、偉大と言うほかない。需要は完全に未知数だったはずである。知らないことを知る機会を与えてくれたことに感謝である。
編著者の中脇聖氏は土佐一条氏の研究を本分としていらっしゃる研究者で、土佐一条氏から派生して行く形で長宗我部氏や明智光秀についても書かれている。編著を引き受けているのは、序章によると氏が今回の企画の仕掛け人だからということらしい。ところで、氏は年来土佐一条氏を「公家大名」や戦国大名の一種とする見方を否定し、あくまでその存在は在国の公家であったと位置付けている。すなわち、何が公家であり、何が大名なのか?ということに常人より敏感であり、特に公家の組織について碩学であるということになるだろう。家司とは何か?という命題を切り拓いていくことに適任者と言えるのではなかろうか。
さて、それでは章ごとに内容を簡単に紹介、感想を書いていこう(正直理解しきれていないところもあるので誤読・誤解などがあれば教えていただけると助かります)。
第Ⅰ部 家司の身分と役割
- 第一章 家司の発生と展開(樋口健太郎)
全ての基幹となる章。本書はどこから読んでもそれなりに読める本だが、出来れば第一章を最初に読むことをおススメする。概念を説明するには、その発生経緯を語るのがもっともわかりやすいと思っているが、この章が家司についてそういう構成になっているからである。律令貴族の家政職員と家司は何が違うのか?中世貴族の家政組織とはどのようなものか?受領家司はなぜ廃れたのか?家司はいかに世襲されていくのか?家司に関する基礎的な経緯が簡潔に明らかにされ、彼らが「権門体制」の末端を確かに形成していたことが理解できるようになっている。
受領家司の時代には、受領家司と摂関家はWIN-WINの関係にあったが、時代が中世に移るとともに、特定の家に奉仕する官僚的な性格を強めている。そして家司は相互の家や権門の間で立ち回るようになる。仕える公家への縦の関係を軸に、横の関係を形成するのが家司という存在とも見受けられた。
- 第二章 家司になった人々(菅原正子)
第二章では日野家の家司について触れられる。第一章が概説だったので、ここからいよいよ具体化・個別化という響きがある。日野家は室町時代、将軍の姻戚となることで地位を向上させた公家であり、家司の人的構造がそれによってどのように変化したのかを探る好例ということだろう。
やや気にかかったのは、37頁において、家司という言葉はあまり使われず、実際には「家僕」や身分を示す「諸大夫」「青侍」「侍」あるいは「家人」「被官」という言葉が使われたと記述しており、一読すると「家人」や「被官」も家司に含まれるのかと思える一方で、39~40頁では家司を挙げた後に「そのほか」として家人・被官を挙げている。家司と家人・被官は包摂概念なのか別概念なのかやや混乱するが、家人・被官として挙げられた本庄氏は個別の列伝で家司扱いされているので、家人・被官も家司らしい。書き分けの意味があったのか、やや不審に見受けられる。本庄氏自体は在地の領主が日野家や足利将軍と関係を深めることで栄達を果たした一例として非常に興味深い。もはや出自が青侍ですらなく、公家社会の言わば外から登用される家司がいたというのは新鮮で、家司が「公家に仕える公家」ではないことを教えてくれる。
- 第三章 山科家家司・大沢久守(神田裕理)
未だ少年で後見してくれる肉親にも事欠く山科言国を補佐し、山科家の家業である衣服の調進に関わる財政を管轄し、装束の故実を収集・記録しつつ、染め物の腕も確かで、山科家の各地の家領の代官任命や年貢受取を一手に担い、その帳面も作成し、山科の郷民を編成、応仁の乱の際は彼らを軍事動員して東軍に味方して軍功を立て、さらには主人言国に教授し朝廷でも披露が可能なほどの「たて花」の名手であったのが大沢久守である。バケモノかな?
特に驚いたのは、軍事に関わった上戦功も立てていることである。背景には久守と郷民の熱い絆が想定されており、団結力やモチベーションも高かったのだろうが、公家は基本的に軍事に深く関与しないイメージが強かったため、余計に家司のマルチタレントぶりが印象付けられた。
ところで、大沢氏の通字は「重」のようで久守も初名は重栄だったようだが、なぜ久守という名前に改名したのだろうか。細かいかもしれないが気になる…。
- 第四章 年中行事から見た家司(遠藤珠紀)
公家と言えば年中行事をこなすのが仕事。それでは家司はどのように年中行事を支えたのかというのが本章。中級公家の家司の実例として近衛家(・鷹司家)の家司の勘解由小路兼仲の活動がまず挙げられている。兼仲は年中行事のマニュアルを作成しつつ、摂関となった主人の申次としての役目も果たしている。要するに秘書的なポジションと見受けられる。兼仲自身「殿中の故実について我が家に及ぶものはあるまい」と自負しており、自分の役割に誇りを持っていた。
その一方で、下級官人の儀式における出仕(本章で触れられているのは粥節供の事例)は、鎌倉時代前期には実務を担う家司が出仕していたが、次第にその場における家司は家柄によって集められただけの存在となり、南北朝時代には儀式自体が有名無実化してしまう。朝廷の衰微もあるのだろうが、主家と家司の関係自体がそもそもドライに見える。
公家の家政が有能で誇り高き秘書の指揮といいように使われる下っ端多数によって成り立っていたことがわかり、現代でも親近感が湧く。
第Ⅱ部 中世摂関家と家司
平安時代末期から鎌倉時代後期にかけての摂関家と家司についての章。この時期に摂関家は分裂し、五摂家(近衛・鷹司・九条・一条・二条)が分立することになるが、家司はこの中でどのように動いたのだろうか。摂関家が分裂することは家司人事に大きく影響するリスクであったため、家司たちは家の維持・分裂回避を図るようになる。藤原基実の夭折後、基通の擁立を図った主体は家司たちであり、平家人脈も加わることで家司の側の力が増していく。家司には公卿に昇進する者も現れ、主従関係というより親族の一種として規定される者も現れる。こうした中、摂関家の実務を一手に握った家司が「執事」として制度化される。ところが、その執事も特定の家により独占され、若年の執事本人より公卿となったその父が実質的に執事を担うようになる。…同時期の鎌倉幕府が執権→得宗→内管領と実権者が移ったのと同じような現象が摂関家にも発生していたのである。
ただし、鎌倉時代中期以降摂関家の実力が衰えると、家司の側も実務を担う旨味がなくなっていく。独り立ちできる家司は家司という立場を放棄してしまうのである。裏返しと言うか、家司が摂関家の維持に拘ったり、執事の位が独占・空洞化されるのも、摂関家が有力な寄生対象だからであった。かくして室町時代以降主家と家司の関係もまた変転していく…。
個人的に面白かったのは、摂関家の分裂と家司の関係である。忠通・頼長の争いで分裂がリスク化→基実・基通の継承で分裂回避とその後の五摂家分立の流れは一読矛盾しているようにも思える。しかして、五摂家分立は家司に実務が丸投げされる→誰が摂関でも実務可能→摂関家分立が可能になる(103頁)と説明されている。分裂による家司間抗争の回避が、特定の家司へ権限を集中させ、もはや分裂のリスク自体がなくなるというパラドックスのような理路が展開されていたのだった。
- 第六章 戦国期、近衛家の家政職員(湯川敏治)
近衛家の家政職員を語る章だが、具体的に挙げられているのは進藤長泰と北小路俊宣である。2人の確認できる職掌は多いが、行事参加や補佐、当主への供奉、奉書の発給など、第三章の大沢久守のようなスーパーマンと言うより、末端の公務員といった感触が強い。興味深いのは収入についてで、進藤長泰も北小路長泰も基本的に荘園からの得分を割り振られていたが、荘園からの収入が途絶してしまうと、収入自体が消滅してしまう。シビアだ…。それでも近衛家は家政職員に得分を割り振れるだけマシであり、細川高国や足利将軍家と接近することでなるたけ荘園収入を維持していた側面が触れられている。不安定な社会の中で何とかかんとか生きようとする切実さを強く覚えた章だった。
戦国期の九条家は言ってみれば「知ってる人は知っている」存在である。九条政基という人物には目を引く要素が多い。家司である唐橋在数を殺害して朝廷から勘当されているし、和泉国日根野荘に下向した際の日記『政基公旅引付』は戦国時代の在地の模様を知る一級史料であるし、実子を細川政元の養子(澄之)に送り込んだことは細川京兆家分裂の一因となった。ある人は「政基にいいところなど何もない」と言うが、面白い人物であることは間違いない。政基の孫も稙通も足利将軍家と対立し、出奔を繰り返すなど波の豊かな人生を送った。
そんな「知ってる人は知っている」彼らより先に家司の信濃小路長盛の評伝が出るんだから世の中すげー。長盛が仕える九条家の当主も破天荒揃いで、彼らの尻拭いに長盛は奔走しているのだが、長盛本人も相当無茶を通したり、おどしとすかししている。知仁親王の元服費用のための借金返済では「どのような方法を使ったのか」(131頁)長盛は返済額を準備したが、絶対に何らかの穏当ではない手段を使ったと想像できる。時代も時代だが、長盛自身に時代を泳ぎ切るパワーを感じさせる。
そんなこんなで長盛は50年以上(!)九条家当主の側近として、当主に振り回されているのか、当主と一緒になって周囲を振り回し続けたのかわからない活動を続けた。武勇も知略も大きくは感じられないが、九条家当主との一蓮托生…というか悪友(?)ぶりが印象に残る。
土佐一条氏は摂関家の一条家から分かれた存在で、土佐一条氏から一条家当主が出ることもあった。言わば両家は別家ながら互換性を有しており、当然家司にも互換性が…と言うよりは、土佐一条氏が別家として成立したという意識も低く、土佐一条氏に出仕していても、京都の一条家へ帰属意識を持つ家司もいたようである。結局土佐一条氏は一条家の土佐在国スペアとして規定され、それ以上の地域権力とならなかったことが、家司という人的な面からも窺えた。
しかし、それでも(源ヵ)康政の存在はやはり注意を引く。康政は一条兼定の下で一手に政治的権限を担うことになる家司である。ただ、だからと言って他の家司がいなくなったわけではなく、意図的な権限集中のようだ。これまでも大沢久守や信濃小路長盛といった強力な家司が存在していたが、彼らはそれぞれの才覚により地位を獲得・維持していたように見えた。彼らに比べると、康政の登用には一条家の意志が示唆されており、一条家の関与を重視する本章では康政目線ではない。ここはかなり重要なポイントと愚案するが、康政の登用を外的要因とするのであれば、なぜ(他の町や長尾らではなく)康政だったのか?という点は気になった。
第Ⅲ部 中世以降の家司の姿
- 第九章 豊臣政権期の家司と官人(水野智之)
第Ⅱ部での見られた家司は決して安定的な存在ではなかったが、それでも主である公家の意向に密接に関わる重要な存在だった。天正12年羽柴秀吉は対立する織田信雄へ与した疑惑で在京していた佐久間道徳を捕えようとする。道徳本人はすでに逐電していたが、付近の住人は捕縛された。その中には勧修寺家、烏丸家、徳大寺家の家司らが含まれており、朝廷はたびたび秀吉に釈放を求めたが、秀吉がこの要求に応じたのは2ヶ月後であった。勧修寺家自体が近衛家の家司であったため、秀吉は信雄家臣の佐久間が家司を通じて近衛家、引いては朝廷をも反秀吉に導こうとする、巨大な陰謀を見たのであった。最終的に近衛家が秀吉に見舞することで陰謀の有無は不明となったが、家司を通じた連携に大きな力があると見なされている。こうした場では、まだまだ戦国期の家司の役割が生きていることが強く印象付けられる事件であったのだろう。
そして、秀吉の政権下でこうした公家の自律性は解体へ向かう。公家の知行は当知行のみが認められることで確定し、そこから脱する者は処罰の対象となった。公家の仕事や役割が設定され、家司も相応の収入を確保できるようになった。それは武家政権に全面的に依存はしているものの、戦国期の不安定さからは解放されたのである。第六章のような光景が発展的に解消されたとも言えるが、個人的にダイナミズムを失ったようにも見える。いや、当事者からしたらそんなことより食い扶持だ!なのだろうが…。
- 第十章 近世堂上公家の家司(西村慎太郎)
この章では久世家の家政構造について、具体的に提示されている。具体性がかなり増し、多様な様相が見えるのは流石近世、江戸時代といった感覚がある。そういった面で注目されるのは男性で構成される「表」の他に、女性で構成される「裏」があり、久世家の妻を頂点とする女性の家司の体系があったことである。妻が家政機関の一員であることは第三章でも若干触れられていたものの、実務や雑用を担う存在がおり、家司に比されるのはやはり驚きがある。家司観がどんどん広がっていきますね。
そして、家司の収入についてはやはり厳しかった。公家自体の収支も厳しく、親しい大名家から援助を仰いでいたが、その無心の文面を書くのも家司なのはちょっとした悲哀である。もっとも家司たちは家司以外の副業もあり(家司の方が副業?)、何とかかんとかやりくりしていたようだ。こうして見ると、第六章→第九章→第十章と来ても経済状況はそれほど好転していない気が…。
- 第十一章 近世公家の家内騒動と家司(田中暁龍)
江戸時代は200年以上大規模な紛争がない泰平の世が続いた。しかし、だからと言って常に平穏無事なわけはなく、幕府にも大名家(藩)にも権力抗争は存在し、戦争にならずとも臨界点を超えることは多々あった。もっともそれくらいのことは知られている範疇に入ると思うが、公家社会にも御家騒動は存在した。…これだけで一冊本になりそうなほど刺激的に見えるが、公家における騒動と家中統制を主題とするのがこの章である。
大きく扱われるのは今出川実種の時期の家中統制である。ピンチヒッターとして7歳にして当主となった実種は本来家司からナメられがちな当主であった。実種は職務怠慢の家司・中川嘉時を謹慎させたり、家法「家内式目」を制定するなど家司統制を図る。この家法の条文が紹介されていたが、「奉公第一」「博打の禁止」「倹約しろ」「依怙贔屓はするな」などありがちなものが並ぶ中で「火の取り扱いに気を付けること。竈の側でうたた寝をしてはならない」というここだけ具体的な条文があり、火の怖さが家法に取り込まれていることに興味を覚える(この家法の2年前に今出川家も火災に遭ったことを念頭に置いているのだろう)。
しかし、寛政4年(1792)家内騒動が起きてしまう。家司たちは連判で家司の1人石田為治の隠居を要求したのである。実種は一時は為治の隠居を許可したものの、事実関係を調査した上で為治に隠居させるような過ちはないと判断、徒党・強訴に加わった家司を処罰、誓約をとった。結果的に家法制定は騒動を未然に防げなかったわけだが、実種も家司を排斥しようとはしておらず、当主と家司は絶えざる緊張関係にあり、家法もその緊張関係の現出の一つと見た方が良さそうである。
家司が出仕しなくなるということ自体は第Ⅱ部まででもあり、処罰を受けることもあったが、それは家司の解任という形であることが多かった。しかし、この章で挙げられる事例は家司の増長ぶりであり、要求を通すのに団結を行なったり、これらに対する処罰も謹慎であって解雇ではない。家司の存在が体制の一部になってしまったため、双方互いを否定することは出来なくなってしまったと推察する。だからこそ互いに互いを規定する家法が騒動への対処として生まれたのだろう。
- 第十二章 近世の公武間交際と二条家の家司(千葉拓眞)
近世においても公武関係は単なる朝幕関係以外に個別の家同士の付き合いがあった。公家と武家(大名)の間には縁戚関係が存在したし、武家が朝廷に贈り物をすることもあった。この章では二条家と加賀藩前田家の関係に家司が果たした役割を見ている。縁組の交渉や前田家から朝廷への献上などに二条家の家司が主体的に関わりサポートを行っている。
しかし、最も大きいのは前田家への金の無心である。前田家と二条家の縁組は18世紀前半には途絶してしまうものの、折に触れて二条家は前田家へ財政援助を要求し、家司は遠く金沢まで出向いて少しでも有利な援助を引き出せるよう交渉している。ここでは家司も主家の利害を素直に代表しているが、自分らの食い扶持にも関わるからだろうか。前田家にとってはその後も縁組の話はあったとは言え、半世紀前に縁組が途絶した家からたびたび援助を要求されるのは災難だが…。
まとめ
流石全12章もあるだけあって、家司を切り口にした公家社会について、かなり行き届いている。官僚であり、領主であり、取次であり、軍事を担うこともある。家司とは実に千変万化な存在だった。しかもその勤務形態も多様で、譜代の家司もいれば、辞めてしまう家司、公家社会外から新しく登用される家司、複数の家に仕えたり、家の分裂によってたらいまわされたり、家司自体が副業だったりする。家司とは何か?は一つのテーマだが、回答を示すのは読み終わっても存外難しい。
個別で見ると大沢久守や信濃小路長盛といった主家に密着し何でもこなしてしまうスーパーマン型の家司が印象に残る。主家の危機に出現する家司は異様に頼もしく、力強い存在だ(「星の昼見えず」でもあるのだろうが)。しかし、名前が印象に残る彼らでさえ、没年が覚束ないのは寂しいものである。スーパーマンでも何でもなく低収入で細々と雑務を担う家司もおり、こちらにはより悲哀を感じてしまう。もっともどちらの家司も、触れられることの少ない中世以降の公家社会が絶えざる動態の中にいたことを強く印象付けているように思う。
ところで、総じて気になったのは「家司」という言葉について。平安時代中期から江戸時代まで公家に仕えて公家社会を支え動かしてきた存在がおり、彼らに連続性や共通する性格があるのは理解された。しかし、そうした存在は必ずしも「家司」と呼ばれたわけではないことも言及されており、本書でも第六章では恐らく意識的に家司ではなく家政職員という語が選択されている。つまり、「家司」とは史料用語ではなく概念用語なのだと思われるが、どのように「家司」が概念用語となったのか、また水を差すようだがタイトルの「家司と呼ばれた人々」は呼ばれてないのでは…という疑問も少し感じてしまう。
そしてもう1つ惜しかったのが、家司の終焉について触れられていなかったことである。現代の日本には公家という身分がなく、よってその社会を支えるべき家司も不在である。家司がいなくなったのは、恐らく明治維新によって公家が消滅・再編されたからだと思われるが、公家と家司の関係はそこで終わってしまったのだろうか。家司は華族やあるいは市民に溶け込んでいき、華族を支える機構へ再生産されなかったのだろうか。こうした点は家司の発生と同様に重要な問題と思われ、そうした論考を読めなかったのは残念だった。
しかしながら、中世以降意識されることの少ない公家社会に注目が集まり、多様な切り口が提示されたことの意味は決して小さくはないと思われる。公家社会は日本社会の一つの断層をなす割にこれまであまり知られてこなかったので、興味を仕掛けるつかみとして家司はかなり大きい存在である。伝奏→家司と来て次に出るのがどうなるのかはわからない(女房とか門跡あたりかなあ?)が、需要と供給のWIN-WINが末永く続くよう応援したい気持ちである。