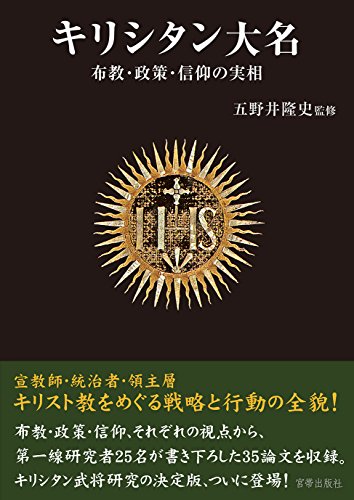戦国時代は世界的には大航海時代と重なっている。ヨーロッパ世界の航海技術が著しく進歩して、ヨーロッパ世界から直接的に人物や文化が流入することが可能となった。そのヨーロッパ世界から最も遠かった国の1つが日本であった。しかし、その日本へも1540年代にはヨーロッパ世界から人物が到来するようになる。当初は九州を中心にして日本列島の人々は大なり小なりヨーロッパ人と交渉を持ち、興味を示すことになる。その結果としてヨーロッパ人が持ち込み布教を行おうとしたカトリックに入信する者たちも出てくる。彼らが真に教義を理解していたかどうかは一概には言えないが、それは間違いなく戦国時代から江戸時代初期を彩った一つの時代の形であった。
キリシタンは地域などで一つの人脈を作っていく。1560年代からは畿内におけるカトリックの布教が活発化し、多くの貴顕にキリシタンが生まれた。彼らは相互に関係しあっており、特に河内国を中心にした人的結合は「河内キリシタン」とも呼ばれている。その動向は三好、織田、豊臣といった中央政権の主宰者たちにとっては無視できないものであり、歴代の政権は彼らを有効活用もしていた。その「河内キリシタン」の代表者とも言えるのが池田教正である。教正は何を行い、何を遺したのか?これを探ることが「河内キリシタン」の時代が確かに存在したことを明らかにする大きな鍵になるだろう。
摂津池田氏と池田教正
池田教正の出自はよくわかっていない。近世の『池田氏家譜集成』は教正は和田惟政の家臣であったとする。また、『長久手戦記』など一部の編纂物は長久手の戦いで教正が活躍したことから、教正を池田恒興の一族とするものもある。しかし、どちらの説も否定される。教正と和田惟政の接点は「キリシタンの保護者」であることのみであり、教正は尾張出身の池田恒興が畿内に来る前から三好氏の家臣として活動しており、恒興の一族とは見なせない。
教正の直接的な出自は不明ながら、初期に摂津で活動していることや摂津の国人と姻戚関係を結んでいること、実名に「正」が含まれることから、摂津池田氏の一族であると見るのが妥当である(なお、摂津池田氏では嫡流に「○正」、庶流に「正○」の名前が多い。ここから推すに教正は嫡流に近い出自なのかもしれない)。それでは摂津池田氏とはどのような氏族であったのだろうか。
摂津池田氏の初見は弘安7年(1284)6月8日に藤原政長が「池田右近尉」と呼ばれているものである(「勝尾寺文書」)。また、同時期に活動が見える「藤原景政(景正)」(右衛門尉)も池田周辺に権益を保持しており(「多田神社文書」)、摂津池田氏と推定されている。南北朝時代に入ると、貞治2年(1363)池田弾正蔵人親政が守護の被官として摂津国賀茂村で半済地を宛て行われている(「今西家文書」)。また、建武3年(1336)には池田氏に近しい岡国茂が池田城に籠っていることを仁木氏から賞されており、池田氏も動向を共にしていたと思われる。
その後一定期間池田氏は見えなくなるが、永享8年(1436)勝尾寺が細川京兆家に巻数を贈った際「池田殿」も含まれており、細川氏被官・在地の有力者として一定の地位が窺える(「勝尾寺文書」)。その直後から池田筑後守充正の活動が具体的に見えるようになっていく。充正は高利貸しとして月1千貫、これとは別に年1万石の収入があると噂され(『蔭涼軒日録』)、応仁の乱にも1000の兵を率いる(『後法興院記』)など摂津国人としての力は突出していく。
その一方池田氏の近隣には伊丹氏もおり、こちらも周辺へと勢力を拡大、池田氏に圧迫された者たちの不満の受け皿として機能し、池田氏と対立を深めることになった。また、池田氏内部においても充正が当主ではあるものの、民部丞綱正や若狭守正種など有力な庶流もおり、惣領家が隔絶した地位を持っていたわけではなかった。
16世紀に入り主君である細川京兆家が分裂すると池田氏もこれに巻き込まれる。永正5年(1508)細川澄元を支持する当主の筑後守貞正は高国方の攻撃を受けて戦死し、当主の地位は池田遠江守正盛に移る(『不問物語』)。永正16年(1519)には貞正の遺児である三郎五郎信正が反高国の兵を挙げる(『細川両家記』)。その後信正は高国に従ったようだが、波多野元清・柳本賢治が高国に謀反すると、高国の波多野攻めの途上で離反し、高国方を敗走させる(『細川両家記』)。信正は細川晴元に与して、その寵臣三好政長(宗三)の娘婿となって筑後守を称し、池田氏当主の地位を固めていく。
しかし、信正は天文18年(1549)その直前の晴元への謀反の責任を取って切腹させられてしまう。池田氏の当主の地位は信正と三好宗三の娘の間の子である長正に移る。この事件をきっかけに三好長慶が晴元に反旗を翻して細川氏に代わって摂津を支配していくが、長正は紆余曲折ありつつも長慶の下で地位を保った。同時に幼い長正を輔弼するためか、池田四人衆(勘右衛門尉正村、十郎次郎正朝、山城守基好、紀伊守正秀)が成立、ここに当主と庶流の関係も一定の落着を見た。
さて、確実な文書における教正の初見は永禄4年(1561)に行われた将軍足利義輝の三好邸御成の準備で三好邸を造立する作事奉行に米村治清とともに「池田丹後守」が見えることである(『三好亭御成記』)。どのようにしてこの地位に登ったのかはわからないが、受領名を称することが出来るのはステータスであり、三好氏の家臣としてそこそこのポジションにいると評価できよう。なお、この御成には三好氏の名目的主君である細川氏綱も参加しているが、氏綱は供として「池田八郎三郎」を連れていた(『三好亭御成記』)。この八郎三郎こそ池田勝正である。当時の摂津池田氏の当主は池田長正であったが、勝正はすでに当主に准じる地位にあったと言える。池田教正と池田勝正、この2人はある意味対照的な人生を送ることになるが、初見が同じであることはある種運命的と言えようか。
その摂津池田氏であるが、永禄6年(1563)2月に当主長正が死去すると、勝正が後継することになる。2月27日には当主勝正と当主を支える池田四人衆が共同で多田神社の利権を安堵し(『戦三』八七五・八七六)、継承は滞りなかったように見える。ところが、3月22日になると勝正は四人衆のうち池田正村と池田基好の2人を粛清し(『細川両家記』)、豊後守と周防守を新たに加える。四人衆が勝正を討つ噂があったともいう(『言継卿記』)。勝正の継承は正統性を有しつつもその家中での地位は絶対的ではなかった。同時期には三好権力も有力者の相次ぐ退場で動揺しており、勝正には当主の地位を確立することが課題として求められていた。
「河内キリシタン」の誕生と池田教正
池田教正がどのようにして池田一族から三好氏の家臣になったのか、その事情は詳らかではない。しかし、永禄期にはその存在が認知されており、後には越水城衆として現れる。越水城は西宮を掌握する摂津国下郡の拠点城郭であり、天文22年(1553)に芥川山城へ移るまで三好長慶の居城であった。その後は下郡一職支配を長慶から命じられた松永久秀が越水城に入り、拠点城郭の機能を引き継いでいる。教正が摂津池田氏の出身とすれば、三好氏が下郡の支配を強める中で長慶、あるいは久秀から編成されていくのも不自然ではなかった。池田教正の妻は同じく長慶に仕えて立身した下郡の国人である野間長久の娘であったが、これも家臣団同士の紐帯を強めるための縁組と見られる。
その後、教正は主君長慶に従って三好氏の新しい征服地である河内へ移った。河内はもともと畠山氏の領国であったが、当主畠山高政が遊佐家中において勢力を伸ばす安見宗房と対立すると、永禄2年(1559)三好長慶は高政の援兵として河内に出兵し宗房を排除した。しかし、翌永禄3年(1560)高政と宗房が和解しともに反三好の旗幟を明らかにすると、長慶は再び河内へ攻め入り、高政・宗房ともに河内から放擲する。長慶はさらに飯盛山城に居城を移し、畠山氏の誰かを擁立するのではなく自身が河内の国主となった。
三好氏の実力による河内平定はそれまで畠山氏内部で下剋上を繰り広げてきた河内戦国史において一つの画期をなす。ただし、その支配には正統性は伴っていなかった。三好氏の家臣として河内に乗り込んできた者もいれば、三好氏に従うことになった河内の国人らもいた。また、地位を上昇させた三好氏は幕臣や細川氏家臣も自身の勢力下に編入する。急速に領国を拡大した三好氏は雑多な従属勢力を編成することを迫られていた。永禄2年(1559)11月には松永久秀の家臣・大饗正虎が楠木氏の正嫡を認められているが、これも河内に縁深い楠木氏の後裔を三好氏が従えることで、河内領有の正統性を担保した一面もあったと思われる。また、永禄3年(1560)11月には飯盛山城に新羅明神が勧請されている(『兼右卿記』)。新羅明神は三好氏の祖先である源義光の護神であり、河内は急速に三好カラーに染められていくのである。
「河内キリシタン」の誕生も同様の契機があると考えられる。上洛した宣教師たちは足利義輝、三好長慶から布教の「允許状」を取得したが、その内容は「禁制」であった。カトリックは既存の宗教と同じ枠組みに入れられて理解されたのである。一方で新宗教であるカトリックへの反発も強い。既存宗教界からの訴えを受けた三好家重臣松永久秀は結城忠正にカトリックの実情を調べさせた。この結城忠正であるが、幕臣結城氏の出身で将軍足利義輝が没落する中も三好氏との関係を重視し、幕臣と三好家臣・松永家臣を掛け持ちする存在であった。ところが、結城忠正本人がカトリックに感銘を受け改宗してしまうのである。結城忠正は儒家であり、三好氏の行政顧問的地位にもあった清原枝賢も改宗に誘い込んでいる。幕臣として名族であり、三好氏の重臣でもある結城忠正と学者としても名高い清原枝賢の改宗は大きなインパクトを以て受け止められた。ここにカトリックは新宗教でありながら、既存の宗教と同様の「強さ」を手に入れたのである。
そして永禄7年(1564)三好氏の家臣73人が飯盛城下においてキリシタンとなった。その中の主だった領主3人として1人目に三箇サンチョが、2人目に池田教正が、3人目に三木半大夫が挙げられている(『フロイス日本史』、教正の洗礼名はシメアン(シメオン))。ただし、この3名はリアルタイムの宣教師の書簡では特筆されておらず、結城忠正と清原枝賢が改宗者として重視されていた。教正がキリシタンとして大をなすのは原因ではなく結果であった。しかしながら、この時点で教正が飯盛城に務めていたことは注目されよう。奇しくも最初の河内キリシタンの代表者3人は、三箇サンチョが河内の国人、池田教正が摂津出身、三木半大夫は阿波出身の三好氏被官と推定され、出自はバラバラであった。三好氏の下で出自が一様ではない家臣団の絆として新宗教カトリックは活用されたのである。
教正がキリシタンとなった永禄7年(1564)には三好長慶が死去した。宣教師の書簡や『フロイス日本史』によると「三好殿」はキリシタンの教えを聞きこれを激賞したと言うが、これが晩年の長慶なのか、長慶の生存を騙るための影武者か、あるいは養嗣子の重存(後の義継)なのか定かではない。さらに翌永禄8年(1565)5月には三好義継は将軍足利義輝を殺害する。この時の義継の軍勢に池田教正や勝正が参加していたかは定かではないが、直前まで義継は義輝の御成を要請していたらしい(「1565年6月19日フロイス書簡」など)。であれば、前回の御成に重要な役割を果たした教正、勝正も準備のため在京していた可能性はある。また、足利義輝を実際に殺害したのは池田教正の息子であるともいう(『足利季世記』)。
三好長慶と足利義輝の相次ぐ死は宣教師やキリシタンにとって庇護を保障する存在の消失を意味していた。三好義継は7月朝廷に宣教師追放を要請し、勅命が下る(『御湯殿上日記』)。もっとも三好氏の宿老三好長逸はほとぼりが冷めるまでと称して、宣教師を堺に安全に護送しており(『フロイス日本史』)、在京できなくなっただけで対応としては厳格ではなかった。
やがて、三好政権はその長逸を中心とする三好三人衆と松永久秀の二派に分裂する。三好氏の家臣たちも三人衆に属するのか、松永氏とともに戦うのか、判断を迫られた。この中で池田教正は松永方となって越水城に籠城する武将として現れる(『細川両家記』)。同じく越水籠城衆の野間長久の娘が池田教正の妻であり、縁故による左袒であろう。しかし、阿波三好家の助力を得た三人衆が優勢であり、越水城も永禄9年(1566)7月には落城した(『細川両家記』)。城衆の1人である瓦林三河守は三人衆方への帰参を認められている(『戦三』)が、教正が帰参を認められたのか、そのまま牢人したのは定かではないが、一定期間活動が見えなくなる。
三好家の争乱と池田教正
永禄9年以降の畿内の戦いは基本的に三好三人衆が優勢であり、池田勝正は三人衆に加担して軍事行動を繰り返している。当主としての正統性を完全に備えていない勝正にとっては、勝ち馬に乗って自らの当主としての力を誇示し続けることが重要であった。また、対立する伊丹氏は松永久秀と親しく、松永方として行動していた。勝正は永禄9年(1566)伊丹氏の領内に放火して「本望」としている(『細川両家記』)。こうした根深い対立関係が池田勝正をして三人衆方の与党とさせていた。一方、池田教正は前述の通り、松永方に与しており、摂津池田氏の動向と去就を連動させていなかった。教正のアイデンティティはもはや摂津池田氏から離れていたと言える。
永禄10年(1567)2月三人衆が擁していた三好義継が三人衆を弾劾し、松永方に移ると、三人衆が松永方を圧倒していたことによる一時の平和は破れることになる。池田教正の動向は後述する永禄11年(1568)の年末まで確かめられないが、三好義継の家臣として動いていることから、前年の越水城落城の折りに牢人したにせよ、帰参したにせよ、この時義継に従ったと思われる。義継の出奔は池田氏の内紛に乗じて行われた(『言継卿記』)ともいうが、想像をたくましくすれば池田教正が何らかの働きかけを行ったのかもしれない。池田勝正はこの後も三人衆の与党であった。
こうして三人衆方と松永方の抗争は再燃することになったが、畿内では前者が優勢なのは変わらなかった。松永方は足利義昭を将軍に就け幕府を再興する勢力の上洛に望みを掛けることになる。そして、永禄11年(1568)9月織田信長が足利義昭を奉じて畿内に兵を進めると、三人衆方は阿波へ撤退し、「天下布武」が実現する。しかし、池田勝正は逃れるべき四国の地などなかった。勝正は池田城に籠城して、織田信長の部将を中心とする幕府軍の攻撃を受ける。幕府軍が池田城を落城させるといったところまで行かなかったため、戦闘面の勝敗については微妙であるが、池田の町が放火されると勝正は結局降伏し人質を出した(『信長公記』)。とは言え、勝正は幕府の敵として断罪されることはなく、池田の領主の地位を認められている。足利義昭・織田信長の目的は室町幕府の再興にあり、池田城一つに長期戦を行うことは本意ではなかった。勝正がそうした思惑を捉え、上手く立ち回ったとも言えるだろう。10月22日に将軍に任官した義昭が参内した際には勝正が伊丹忠親とともに警護を担当しており(『細川両家記』)、勝正は義昭幕府を支える大名に転身した。
ただし、三人衆方の勢力は温存されていた。12月29日に畿内に渡海した三人衆の軍勢は和泉の家原城を攻めて落城させた。この時城主の寺町左衛門大夫と雀部兵衛尉は戦死した(『細川両家記』)。同時に池田教正が戦死したという情報もあり(『多聞院日記』)、教正戦死は誤報であるが、家原城に務めていたのかもしれない。家原城は三人衆の反攻を防ぐ拠点であり、教正の能力が評価されてのことだろうが、ここでは九死に一生を得たこととなる。三人衆の軍勢はそのまま京都まで駆け上り、義昭の御所であり本圀寺を包囲する(本圀寺の変)。しかし、救援として三好義継、池田勝正、伊丹忠親らの軍勢が駆け付けたため、三人衆の軍勢は退いた。特に池田氏では四人衆の一人でもあった池田一狐(正秀)が活躍している(『信長公記』)。畿内の大名層の呼応が広がらなかったのが三人衆の敗因だったが、その一方三好義継や池田勝正にとっては幕府の一員であることをアピールする戦いであった。そのため彼らは戦意が高かったのだろう。
さて、一方のキリシタンであるが、禁教令は未だ続いていた。宣教師たちは三人衆や篠原長房にも掛け合っていたが、この件に関しては三人衆が奏上しても朝廷の側から禁教令の解除が許されなかった。続いて、足利義昭・織田信長が上洛すると、宣教師たちは今度は義昭・信長に期待をかけた。特に義昭幕府の有力者として山城と摂津の「副王」と見なされていた和田惟政はキリシタンの保護に積極的で、永禄12年(1569)3月に堺にいるフロイスの上洛を呼びかけた。この時フロイスの荷物を富田からフジ(Fuji)まで運び高山飛騨守に託したのが池田教正だった。つい数ヶ月前家原城で死にかけた様相は全く感じさせない。上洛したフロイスのもとには結城忠正、池田教正、高山飛騨守をはじめ多くのキリシタンが挨拶に赴いた(「1569年6月1日フロイス書簡」)。三好氏の下で培われたキリシタンの結びつきは不変であった。
ところで、摂津の「副王」とも呼ばれた和田惟政であるが、惟政は三好氏の本拠地であった芥川山城を与えられ(後に高槻城に移る)、上郡のみならず下郡にも文書を発給し、越水城も管轄していた形跡があるなど、単なる高槻周辺の領主でなく、摂津広域に権力を行使する存在であった。池田勝正や伊丹忠親も幕府に直属する存在として独立していたが、その統治範囲は基本的に池田・伊丹周辺に限られる。和田惟政と池田勝正・伊丹忠親は決して同列の存在ではなかった。このことを示すように、永禄12年(1569)10月の幕府による播磨攻めでは和田惟政が池田・伊丹両名を率いて出陣している(『細川両家記』)。
元亀の争乱と池田教正
義昭幕府は元亀元年(1570)に大きな岐路を迎える。その発端の一つが摂津池田氏の分裂であった。足利義昭は織田信長の成敗権を与え、4月に幕府に従わない越前の朝倉義景を攻めさせた。ところが、朝倉氏を攻めるまでに北近江の浅井長政が幕府から離反し、幕府軍は撤退に追い込まれる。この時殿軍を務めたのが木下秀吉、明智光秀に加え、池田勝正であった(「武家雲箋」)。特に勝正は3000の兵数を率いて幕府軍に参加しており(『言継卿記』)、未だ小身の木下、明智に比べると大きな力を持っていた。殿軍も勝正が大将格だった可能性があるだろう。それは同時に勝正ら池田の軍勢がもっとも消耗を強いられたとも言える。
義昭幕府成立以来、池田勝正はその与党として忠実であった。ただし、勝正は永禄12年(1569)より今井宗久から堺五ヶ庄内部の善珠庵分を押領したとして激しく訴えられている(「今井宗久書札留」)。また、但馬攻めも播磨攻めも越前攻めも従軍したものの得るものは何もなかった。勝正は成功を重ねることで、当主の地位を確立しようとしていたが、幕府に従って以来は勝正の努力とは無関係な部分で失敗続きであった。池田家中は徐々に勝正の求心力からは離れていく。
6月19日ついに池田勝正とその家中の対立は臨界に達した。池田家中は池田四人衆の池田豊後守と池田周防守を殺害し、勝正を放逐した(『言継卿記』)。ここに四人衆体制は終焉を迎え、家中の有力者が二十一人衆を組織して池田氏を運営する体制となった(『言継卿記』・「中之坊文書」)。ただし、二十一人全員が同格ではなく、四人衆を務めたこともある池田一族の長老・池田一狐と勝正の代に勢力を伸張した荒木一族を束ねる荒木村重の2人が中心人物であった。また、池田民部丞を名乗る人物が池田氏の当主となったようであり、禁制を出している(「離宮八幡宮文書」・「勝尾寺文書」)。
義昭幕府は敏感に対応し、20日には上野秀政、細川藤孝、一色秀勝、織田信広らが山崎で示威行為を行った(『言継卿記』)。放逐された勝正は三好義継を頼り、26日に義継の手引きで上洛する(『言継卿記』)。勝正が幕府を頼ったことで、池田家中は三人衆との連携を模索する。これに呼応して三人衆の三好宗功・生長父子が池田城に入り、ここに池田家中は反幕府方となった。
三好三人衆は本願寺も蜂起させ、摂津方面において幕府に対し優位に立つ。12月には松永久秀が仲介して、三人衆と織田信長は和睦に至るが、三人衆は畿内に地歩を築くことに成功した。だが、足利義昭にとっては三人衆は未だ「御敵」であり、また和田惟政は摂津の大名として自身の領域が冒されることに強く反発があった。和睦が成立したとはいえ、摂津では一触即発の状態が続き、松永久秀は幕府内での立場を悪化させた。元亀2年(1571)5月ついに松永氏は三好義継を盟主に三人衆と連繋し、幕府方の和田惟政や畠山秋高を攻撃して幕府から離反した。幕府も7月以降軍事行動を活発化させ、8月2日には池田勝正が原田城に入城して池田城を臨む(『国賢卿記』)。相変わらず、幕府方の勝正、三好方の池田家中(池田一狐・荒木村重)という構図にあった。
そして、8月28日郡山で和田惟政と荒木村重ら池田軍が激突し、和田勢は惟政が戦死する大敗を喫した。高槻城はその後松永久秀と篠原恕朴に包囲され、三人衆は三好義継を高槻城に入れることを図る(『二条宴乗記』)。ここに永禄11年以来の幕府の摂津支配は大きな危機を迎えた。明智光秀や佐久間信盛が高槻城の援軍に出来し、三好方は包囲を解除した(『尋憲記』)が、脅威が去ったわけではない。何より、惟政の遺児・愛菊(惟長)は幼少で、最前線の役割は果たせなかった。
幕府方が採った打開策は三好方の大きな切り崩しであった。三好義継・松永久秀と三人衆の連繋で存在価値を低下させつつあった細川六郎(昭元・信良)と石成長信がこれに応じ、前者は京兆家当主の地位を公認、後者は山城郡司に任命されることで、幕府方となった。また、幕府方は摂津の争乱の原因として池田と伊丹の対立を見ており、両者の和解を図っている(「細川家文書」)。この結果、池田家中も幕府方に帰参したようで、元亀3年(1572)1月には「手替」をした「池田・石成」の案内で幕府方が反攻に出ることが予想されている(「誓願寺文書」)。ただし、この結果足利義昭は池田勝正を「一切不能許容」(『土佐国蠢簡集拾遺』)とし、勝正を見捨てた。池田家中の分裂は修復されなかったのである。
しかし、こうした大きな切り崩しと大胆な方針転換にも関わらず、幕府方は大きな反攻に出られなかった。元亀3年(1572)4月には幕府内で役割が低下していた和田惟長と相変わらず池田氏と仲が悪い伊丹忠親が三好義継に接近し始め、また摂津中島城に入った細川昭元も数ヶ月で破綻するが義継と和睦を結ぶ(『戦三』参考121)。結局従来の対立関係は何ら清算されておらず、幕府の求心力も万全ではなかった。
また、三好義継も摂津方面の進出は挫折したものの、山城・河内南部方面へは頻繁に軍事行動を繰り返していた。この中で池田教正も多羅尾綱知と連署し、牧郷から八尾周辺の普請への動員を図っている(『戦三』一六八五)。教正が義継の居城である若江城を守っていた時、畠山氏に通じた3人の武将が反乱しようとするも、義継に反乱が通報されて未然に防ぐという事件もあった(「1573年4月20日フロイス書簡」)。教正は義継の軍事行動を支え、本拠の留守を任されるなど信頼された重臣であった。永禄年間の教正は影の薄い存在だったが、元亀の争乱に乗じて地位を向上させていった。
そして元亀3年(1572)年末にかけて、幕府内でも足利義昭と織田信長の関係が急速に悪化し、事態はさらに混乱する。元亀4年(1573)2月義昭は信長に対し蜂起するが、畿内勢力の反応は分かれた。信長は和田惟長を通じて伊丹忠親を味方にしようとする(「細川家文書」)が、伊丹忠親は義昭に従い京都へ兵を送った。池田家中も池田一狐と荒木村重は別々に動き、一狐は幕臣に加えられて義昭に味方する一方、荒木村重は高山右近を内通させ、和田惟長を襲撃、高槻城を奪った上で織田信長に従った。義昭は三好義継を赦免したものの、義継は上洛せず京都周辺に大軍を待機させて事態を静観した。皮肉にも幕府が分裂することが、従来の対立関係を大胆に清算することになった。義昭と信長に和解の可能性も残る中、荒木村重は独力で勢力を拡大し、逆に三好方は時間を空費した。
気付けば、足利義昭は追放され、織田信長が京都周辺に覇権を固めつつあった。11月信長は佐久間信盛を派遣して義継の若江城を攻める。義継から多羅尾綱知・池田教正・野間康久らが離反し、佐久間軍を城内に引き入れたため、義継は切腹した(『信長公記』)。どのような理由で教正が義継を裏切り死に追いやったかを語る史料はない。教正は元亀の争乱の中で義継の信任を受け重臣として成長してきたと思しく、積極的に義継を死に追いやる理由があるとは思えない。あるいは、義継の方が死を選んだのかもしれない。
ともあれ、池田教正は織田氏の家臣に転じることとなった。同時に摂津池田氏は荒木村重に下剋上され、池田勝正は没落、池田一狐も津田宗及の茶会に出席し続ける(『天王寺屋会記』)もののもはや勢力はなかった。ある意味元亀の争乱によって教正は初めて独立独歩の立場となったとも言えよう。
若江三人衆としての池田教正
三好義継の滅亡によって、すんなり北河内が織田領になったかと言うと、そうではなかった。翌天正2年(1574)4月には畿内勢の残党が本願寺に入っている(このメンツに池田勝正がいるのが勝正の最後の記録である)が、その中には三好氏の遺臣である松山氏もいた(『永禄以来年代記』)。そして、8月頃松山氏と本願寺は手を結び、飯盛城下に出兵、織田方の明智光秀・長岡藤孝・筒井順慶らと交戦した(「細川家文書」)。織田氏に従わない三好氏の旧臣も健在であり、北河内統治もまた安定していなかった。
一般に義継滅亡とともにその旧領(北河内)統治が多羅尾綱知・池田教正・野間康久に委任され、彼ら3人は若江三人衆と呼ばれるようになったとされる(『信長公記』)。ただし、若江三人衆という言葉の初出は天正6年(1578)頃で、3者が共同しているのも天正3年(1575)12月が最初である(いずれも『天王寺屋会記』)。義継滅亡直後から若江三人衆が成立していたのかは定かではない。むしろ山城・大和の「守護」となった原田直政を上司に、三好残党へ対抗しつつ徐々に三好人脈の再編が進められたのではないだろうか。天正3年(1575)には南河内の三好康長が織田信長に従属してその地位を認められ、河内は北部を若江三人衆、南部を三好康長が公権を代表する体制が整った。
かくして池田教正は若江城に拠って、三好義継以来の地位を受け継ぐことになった。しかし、それは多羅尾綱知や野間康久との共同統治であった。文書上、軍事上こうした編成の問題点は浮かび上がってこないが、教正が熱心なキリシタンであり、対照的に多羅尾綱知は激烈な反キリシタンであることから、宗教をめぐる事件がいくつも起こった。多羅尾綱知はキリシタンとして有力な三箇サンチョを讒言したが、佐久間定盛と池田教正が織田信長に申し開きをして事なきを得た。さらに綱知はサンチョを失脚させるに邪魔な教正を遠ざけるため、佐久間定盛の子・定栄の書状を偽造して教正を出陣させた。この時も謀略に気付いた定盛が教正を呼び戻したため大事に至らなかった(「1578年7月4日フランシスコ書簡」)。
このように反キリシタン激しい同僚がいることは池田教正のキリシタン活動には重荷であった。天正4年(1576)京都に南蛮寺が出来た折には、畿内のキリシタンがこれに協力したが、教正は織田氏に対立する和泉の寺院を焼き討ちついでに壮麗な鐘を奪い京都まで運んだものの、畿内のキリシタンとしては4番目と評され、河内岡山の領主結城弥平次(ジョルジ、忠正の甥)よりも劣る扱いだった(「1577年9月19日フロイス書簡」)。高山右近の高槻には8000人、三箇サンチョの三箇には4000人、結城弥平次の岡山には2000人のキリシタンがいた(「1579年12月10日カリオン書簡」)のに対し、教正の八尾(天正8年頃若江から八尾へ三人衆は拠点を移した)には800人のキリシタンがいる(「1582年2月15日コエリュ書簡」)のみで大きく立ち遅れていた。
特に高山飛騨守が三箇や岡山の祝祭を見て、高槻の祝祭がこれに劣らないようにした(「1577年7月22日コエリュ書簡」)ことや、三箇は若江に、岡山は三箇に、高槻は他のところに祝祭が劣らないよう意識していた(『フロイス日本史』)ことを踏まえると、キリシタンの祝祭は新興キリシタン都市の発展競争であった。池田教正は八尾にフロイスが訪れた時、夫人や息子とともに饗応し、フロイスが去る際には家臣総出で見送っている(「1581年4月14日フロイス書簡」)。教正の意志も周囲に負けるものではなかったが、独立した領国がないことが布教の妨げとなっていた。
だが、天正7年(1579)頃から若江三人衆の序列も変化する。若江三人衆は書札礼上、多羅尾綱知>野間康久>池田教正の序列にあり、若江城本丸に多羅尾綱知、二の丸に野間康久、三の丸に池田教正が居住していた伝承もある(「若江三人衆由緒書上」)。しかし、多羅尾綱知の地位が多羅尾光信に代わると、書札礼における順位は池田教正>多羅尾光信>野間康久と教正がトップに躍り出る。事情は詳らかではないが、先述した多羅尾綱知の書類偽造などへのペナルティだったのかもしれない。
教正は河内の領主の紐帯にもなっていた。教正の娘マルタは結城ジョアン(忠正の孫)に、他の娘は畠山旧臣で烏帽子形城周辺を統治する3人の領主の1人(碓井定仙?)の息子と、多羅尾光信(コエリュは光信に改宗の期待を示しており、光信は綱知と違って反キリシタンではなかったようだ)に嫁いでいた。特に教正は三箇の謀反疑惑払拭に努めた一方、烏帽子形の領主が亡くなった際織田信長から改易されそうになったのを、自身が娘婿を後見することで防いだ(「1582年2月15日コエリュ書簡」)。教正こそが河内の有力者を結びつけ支える存在になっており、三人衆における立場上昇とも陰に陽に関わるものだろう。
こうした中、教正は若江三人衆による共同統治を清算し、北河内を分け合った上で独立した大名になることを望みだしたようである。教正は八尾の教会が小さく2つしかないことに不満を募らせていた。先述したように立派な教会を持ちその庇護者として振舞うことは畿内キリシタンの「競争」でもあった。教正には自分こそが河内キリシタンのリーダーである自負があり、自分がそのネットワークの中心となることで上方を統治する自信があったのだろう。しかし、織田信長がこれを認めることはなかった。天正8年(1580)に本願寺を屈服させた後の信長は畿内直轄化に乗り出しており、摂津では高山右近が旗本扱いされる一方、中川清秀は中国地方への国替えが予定されていた。信長の構想の中では北河内も直轄地か一門領となる予定のはずで、若江三人衆がそれぞれ独立大名化する道はなかったのではないか。
豊臣政権と池田教正
ところが、織田信長は畿内統治構想を明らかにせぬまま、天正10年(1582)6月2日惟任光秀に襲撃され横死することになる(本能寺の変)。若江三人衆が四国へ出陣する戦力に数えられていたのかは直接的には不明だが、すぐに河内に戻り情勢を判断することが求められた。三箇サンチョは織田政権での扱いに不満があったものか(光秀からは河内半国と黄金を積んだ馬1頭を褒賞に約束されたという)、惟任光秀に味方することにしたが、反キリシタンの武将たちはこれを見逃さず、三箇の教会を焼き討ちし、河内三箇氏は没落してしまう(「1582年11月5日フロイス書簡」)。河内での織田対惟任の戦いは宗教対立も絡んだものとなったが、この時教正がいかに動いたかはわからない。
しかし、惟任光秀は畿内の諸士の統率に成功した信長の三男・信孝といち早く戻ってきた宿老・羽柴秀吉によって、6月13日には敗死に追い込まれた。教正や若江三人衆がその後罰せられた形跡もなく、恐らく信孝に従ったものだろう。27日には信長亡き後の織田家の統治体制が話し合われ、織田家は羽柴秀吉、柴田勝家、惟住長秀、池田恒興の4宿老による合議制へと移行することになる(清洲会議)。河内国は羽柴秀吉に与えられることになった(『多聞院日記』)。若江三人衆は新しい上位権力者に相対することになったのである。なお、10月8日織田信長の葬儀を3日後に控えた教正は、家を買い上げて終日の酒宴を催している(『天王寺屋会記』)。
もっとも秀吉と河内国は元来関係性が希薄であった。秀吉はひとまず北半国を若江三人衆が、南半国を三好康慶が統治する体制を温存した。しかし、秀吉は河内を支配していかねばならない。秀吉は10月には若江三人衆をはじめ畿内の勢力から人質を徴収している(『戦三』参考147)。12月には若江三人衆に徴税を命じている(『戦三』一九四三)。若江三人衆の統治を認めつつもそれを秀吉の管理下に置こうとする目論見が窺える。
秀吉が河内を支配して行く上でもう一つの大きな事案は秀吉の甥が三好康慶の養嗣子に入ったことである(三好信吉、後の豊臣秀次)。これは康慶の養嗣子に入っていた信孝が岐阜城主となり織田に復姓したことに伴う処置と思われる。しかし秀吉としては、自身の血縁が三好氏の後継者となったことは様々な点で大きい。河内の支配体制は北を三好義継旧臣が、南を三好康慶が治める体制であったため、信吉を通じて旧三好人脈を正統性を以て吸収することが可能となった。当然、若江三人衆の動向もまた信吉と不可分のものとなっていく。
新生織田政権の合議制は長く続かなかった。宿老である羽柴秀吉と柴田勝家の対立が起きると、秀吉は織田信雄、勝家は信孝と結んだ。この対立は天正11年(1583)3月の賤ヶ岳の戦いにおいて羽柴方が勝利し勝家が敗死することで決着した。こうして秀吉は織田氏の重臣でありながら、宿老中でも地位を突出させることになった。さらに秀吉は大坂城を新規築城し始め、天下の主宰者であることをアピールする。秀吉は主君として信雄を擁立したが、こうなると信雄との対立は必至であった。天正12年(1584)3月には信雄は秀吉と懇意であった三家老を抹殺し、秀吉と交戦することになる(小牧の戦い)。この結果信雄は秀吉に屈服することになり、織田政権の体制自体が完全に崩壊に至る。
若江三人衆はどうなったのだろうか。賤ヶ岳の戦いには若江三人衆からは参戦が見えない。畿内においても泉南・紀伊の勢力が反羽柴方として動いていたため、河内・和泉の兵は予備として留め置かれたのかもしれない。賤ヶ岳の戦いの後、戦後処理に乗じて秀吉は畿内の直轄化に乗り出す。荒木村重滅亡後摂津国下郡を治めていた池田恒興は信孝の遺領である美濃へ移った。ここにおいて若江三人衆も解体され、教正は河内を離れて美濃の領主となったのである。他の河内キリシタンも同様であった。
ただし、単に迫害されたわけではなく、教正は美濃へ移るにあたって俸禄と地位は倍増したという(「1584年1月2日フロイス書簡」)。三好信吉は池田恒興の娘婿となっており、美濃へ移ったのは三好旧臣として信吉と恒興を結びつけつつその与力となったということだろう。なお、美濃移封前の池田恒興の領地には池田が含まれており、紀伊守と他称される(息子の元助は紀伊守を名乗っている)。「池田紀伊守」は摂津池田氏の有力者であった正秀(一狐)の受領名であり、恒興は摂津池田氏に連なりつつも「荒木村重」ではない名前として「紀伊守」を選んだのかもしれない。後世には教正は恒興の一族と誤解されることもあったが、恒興の尾張池田氏が自らを摂津池田氏に擬そうとした努力が背景にあったのかもしれない。
以上の経緯から、小牧の戦いでも教正は恒興や信吉とともに行動した。しかし、長久手の戦いで池田恒興・三好信吉の連合軍は大敗を喫し、恒興とその子元助は戦死する。この長久手の戦いで教正は300人の兵を率いたが、敗北の中金の十字架を掲げて敵中を突破し生還、その武名は轟いたという(「1584年8月31日フロイス書簡」)。事実であれば、有名な関ヶ原の戦いでの島津氏のいわゆる「敵中突破」を20年先駆けて行ったことになる。教正が活躍したのは事実のようで、『太閤記』においても教正軍が奮戦したため、織田・徳川勢は手を出さず、恒興らが討たれ敗北が確定した後教正軍は撤退したとする。なお、この合戦で結城ジョアンは戦死しており、教正は戦後孫にあたるジョアンの遺児2人を引き取っている(「1585年10月30日セスペデス書簡」)。
その後も教正は秀吉から小牧の戦いの戦後処理について連絡されており(『戦三』一九五九・一九六〇)、地位を認められていた。教正は天正13年(1585)頃からは本格的に豊臣秀次(三好信吉)の家臣に転じ、8000石の収入を得たという(「1585年10月30日フロイス書簡」)。天正15年(1587)6月には秀吉が伴天連追放令を出し、大名では高山右近がキリシタンであるゆえに大名の地位を失ったが、教正はともに秀次に仕える庄林コスメとともに「棄教するつもりはないので、キリシタンとして仕えられないのであれば、お暇を頂戴したい」と言ったが、秀次は両人に引き続いて仕えることを許している。秀次は年老いた庄林コスメと語らうことを好み、キリシタンが多いとして花正に領地を与えている(「1592年10月1日フロイス書簡」)。教正についても同様で、畿内戦国をよく知るベテランを手元に置いておきたかったのだろう。
教正のキリシタンとしての活動は続き、1588年には他の畿内系のキリシタンと連署してローマ教皇へ書状を送っている(『戦三』一九七六)。尾張では教正とその娘婿・庄左衛門(名字は不明)、アロイジアという婦人がキリシタンの代表として挙げられ、父親に逆らってキリシタンとなり出奔した息子を教正が匿うなどキリシタンの庇護者としても動いている(「1595年2月14日オルガンティーノ書簡」)。ただ、全体的に宣教師の書簡においても教正は影が薄くなる。教正をキリシタンの第一世代とすると、この頃には第一世代の子の世代にあたるキリシタンに活動の力点が動いていた。
秀次家臣としての教正はよく働き、秀次の重要な所領の1つである清須において町奉行を務め、町の調査や堤の修造などの民政を担った(『駒井日記』・『戦三』一九八〇)。ところが、文録4年(1595)秀次が豊臣政権内で失脚、自害すると、教正もまた地位を追われ、庄左衛門ととも九州に追放された(「1596年12月13日フロイス書簡」)。肥後のキリシタン大名小西行長は結城ジョルジュや内藤ジョアンら追放されたキリシタンの要人を保護・登用しており、教正が移った九州も行長のツテを頼ったのかもしれない。
池田教正の「後裔」
追放後の池田教正の動向は杳として知れない。関ヶ原の戦いによる小西旧臣の牢人にもその後のキリシタン弾圧にも教正の名は語られることはなかった。こうしたところを見るに、教正は慶長元年(1596)以降程なく、少なくとも豊臣秀吉の死に起因する政争・戦乱を見ることなく死去したと思われる(自害説もあるが、キリシタンである教正が自殺を選ぶとは思えない)。教正の初登場から30年以上が経っており、おそらく教正は60歳前後に達していた。寿命が尽きたのだろう。年老いてから縁もゆかりもない九州に移ったのも一因かもしれない。
そして、キリシタンを庇護していた小西行長は関ヶ原の戦いで敗れて改易され、禁教令が拡大していくと、もはやキリシタンの武士は日本に居場所を失う。彼らは棄教するか追放されてしまうのである。池田教正の子孫がどうなったのか、定かではないが、キリシタンであることはアイデンティティではなくなってしまっただろう。
ところが、江戸時代前期に「池田教正」は再び姿を現すことになるのである。これは一体どういうことか?新たに出現した「池田教正」とは何者なのか?
江戸時代には「太平記読み」と言われる講釈師が隆盛し、『太平記』の注釈書が数多作られた。そのうちの1つ『太平記評判秘伝理尽鈔』では巻38「和田楠摂津ノ地ニ発向ノ事」において「池田教正ハ、正行ガ息男也」として、楠木正行の子として「池田教正」を登場させ、勇気と忠義によって楠木正儀を撃退したことを語っている。
さらに、『太平記評判秘伝理尽鈔』とともに伝来されることの多かった『恩地左近太郎聞書』では「池田教正」の出自について次のように語られる。
正行二、三歳ノ幼童アリ、多門丸ト号ス。内室又一子ヲ孕メリ。是ハ摂州野瀬ノ庄ノ住人内藤右兵衛尉満幸カ娘也。(略)正行討レテ後(略)、満幸カ方ニ帰シ遣リヌ。程経テ産平安ニシテ、一人ノ男子ヲ生リ。其後同国ノ住人池田九郎教依、此娘美人タルヲ聞テ内藤ニ所望シテ夫婦ノ契ヲナセリ。件ノ子ハ大剛ノ者ノ子ナレハ、某養子ニセンスルコソトテ、池田十郎教正ト名乗セケリ。後ニ細川武州入道ノ手ニシヨクシテ、数度ノ戦ニ武功ヲ顕シ、世ニ武ノ誉アリシ池田兵庫助是也。(略)今ノ池田ノ六郎ハ教正ニハ孫、佐正ガ子也トニヤ。
なんと、「池田教正」は楠木正行の子であり、同時に摂津池田氏の祖となったというのである。実際の摂津池田氏は鎌倉時代から一貫して藤原姓であるし、南北朝時代にここで言う教依や教正がいた形成もない。そもそも、この説の初出は『恩地左近太郎聞書』であり、『太平記』に遡るものではない。
しかし、「池田教正」が創作名であるにしては、実在の戦国武将池田教正と実名が完全に一致するのは見逃せない。恐らく、この話の創作者は実在の池田教正をよく知る人物ではなかろうか。これを補強するかのように、江戸時代後期の『太平記評判秘伝理尽鈔』の注釈書『陰符抄』では、『太平記評判秘伝理尽鈔』の作者大運院陽翁の出自を波々伯部氏であり、父は「三好殿」次いで豊臣秀次に仕えたとする。また、河内に本拠地があったという。これが事実であるかどうかは何とも言えないが、陽翁の父の経歴が実在の池田教正と一致することには注意を払いたい。
また、『足利季世記』によれば、池田教正の息子は将軍足利義輝を殺害した人物であり、その後盲目となって琵琶法師として「三好検校」を称したという。これまた事実であるかどうかは留保される記事だが、教正の息子は実在が確かめられるものの異様に影が薄い。教正には多くの娘がおり、キリシタンや教正の同僚に嫁ぐことで縁戚関係を作っており、彼女らもまたキリシタンであった。しかし、宣教師たちは息子については存在を書き残したものの、その信仰への態度や人格に触れることはなかった。また、年老いた教正に代わって息子が活動した形跡もない。こうしたところを見ると、教正の息子が不具者であった可能性は高いのではなかろうか。芸能民という末路も「太平記読み」との親和性を強く感じさせるものでもある。
なお確言に足らないが、『太平記評判秘伝理尽鈔』が作られた環境として、三好氏の旧臣、さらには実在の池田教正をよく知る人物が積極的に関わった可能性は大きいと思われる。流石に時節柄キリシタン要素は加えられていないが、三好氏が河内を支配するにあたって、楠木氏の名跡を利用しようとしたこと、摂津池田氏出身であろう池田教正が河内の領主として縁戚関係を展開したことを、「楠木氏の子である池田教正が摂津池田氏の祖となる」物語は織り込んでいると言える。
ここに河内キリシタン・池田教正は文学の世界で「転生」を果たし、語り継がれることになったのであった。実在の池田教正の記憶は失われるに惜しいものであった、そうした思いが「転生」を可能にしたのであろう。
参考文献

- 作者:中西裕樹
- 発売日: 2019/08/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)